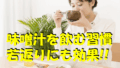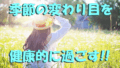休日にしっかり休んだのに、なかなか疲れが取れない…。
こんなことを感じたことはありませんか?
忙しい日々を送っていると自分でも気付かないうちに疲れを溜めてしまいがちですね。
多少の疲れなら無視して頑張ってしまう。しかし、疲れは体からの危険信号ですからね。その疲れを解消せず放置していると心身に大きな負担がかかってしまいかねません。
疲労といっても仕事・人間関係・運動・育児など、いろいろな疲れがあります。それって、もしかしたら脳の疲れが原因かも知れませんよ。
無理を続けていると病気になってしまう可能性もあるし、適度に休養を取りリフレッシュすることが重要ですね。
そもそも疲労とは
なんとなく体が重くてやる気が出ない。最近、寝起きが悪い・・・。疲れがたまっているのかな?
疲れがたまっていると心身の調子が悪くなって体のパフォーマンスも落ちてきます。そして、肉体的な疲れと違い精神的な疲れは自分でも自覚しにくい部分があります。
でも精神的なものも肉体的なものも、疲れは無視してはならない体からのサイン。疲れは痛みや発熱と並び、体が発する危険信号の一つでもあります。
放置していると身体が正常な状態を保てなくなってしまうかも知れません。
日本疲労学会は、疲労を、過度の肉体的および精神的活動、または疾病によって生じた独特の不快感と休養の願望を伴う身体の活動能力の減退状態。と定義しています。
そして疲労は、『末梢性疲労』と『中枢性疲労』に分けられます。
末梢性疲労とは、体を酷使することで生じる肉体的な疲労のこと。身体を構成し働らかせるための材料となる物質やエネルギーが枯渇した状態です。
それと筋肉だけでなく内臓も使い過ぎると機能が低下して疲れるんです。筋肉に比べ内臓の疲れは気付きにくく、自覚症状がないまま重症化するケースも少なくありません。
一方の体を動かしていないのに精神的に疲れたと感じる場合や、神経が疲労している場合のことを中枢性疲労と言います。
長時間の会議をしたり、パソコンに長く向き合って作業したりしていると、ぐったりする状態ですね。あと人間関係に悩んで同じような疲れを感じることもあります。
疲労の原因とは
疲労には肉体的なものと精神的なものがありますが、実は肉体的な疲れにも精神的な疲れにも共通する原因があると考えられています。
運動すると筋肉の中に増えるのは『乳酸』という物質が疲労の原因でした。でも、近年では、疲労の原因だと考えられているのは活性酸素による『自律神経』へのダメージと言われています。
自律神経とは、意思とは無関係にはたらき、その時々の状態に合わせて身体をベストな状態に保ち続ける神経の総称ですね。
暑いときに汗をかいて体温の上昇を抑えたり、運動時に鼓動を早くして筋肉により多くの血液を送ったりと身体にとって重要なさまざまな役割を果たしています。
『自律神経』には互いに相反した働きをする『交感神経』と『副交感神経』に分けられるのはご存じですよね。
緊張したり興奮したりしているときには交感神経、リラックスしているときには副交感神経が優位になります。
身体を動かし過ぎたり精神的なストレスを感じ過ぎたりすると自律神経のバランスが崩れ『活性酸素』が大量に生成されます。
活性酸素とは、呼吸によって取り込まれた酸素の一部が体内で活性化された物質のことです。
免疫機能など、体に不可欠な働きをするんだけど、増え過ぎると細胞を傷つけ、がんや心血管系疾患、生活習慣病などの病気を招く要因にもなると言われています。
で、体内には活性酸素の悪い働きから身体を守る機能が備わっています。でも活性酸素の生成がこの機能を上回ってしまうと活性酸素が神経細胞を傷つけ疲労が生じるのです。
また加齢や紫外線、睡眠障害なども活性酸素を増やす要因で疲労を招くと考えられています。
疲労が心身に及ぼす影響
疲労は身体からの危険信号の一つになります。溜まった疲れを無視し続けていると心身に大きな悪影響が及んでしまう場合もあります。
疲労が身体に及ぼす影響としては、身体のだるさや肩こりなどの筋肉の痛み、眼精疲労などですね。特にデスクワークでパソコンなどの長時間仕事などは、肩こりや眼精疲労に悩まされている方は多い。
疲労が長い間にわたって積み重なると『蓄積疲労』と呼ばれる状態に陥ってしまいます。蓄積疲労の状態になると休養や睡眠をとったり、栄養を摂取したりしても、なかなか疲労が解消できず、回復が困難になっていきます。
疲労の影響は身体だけでなく精神にも表れます。最近では、脳の疲れも指摘されています。
そう、脳だって疲弊してしまうのです。怒りっぽくなったり、勘違いやど忘れが増えてしまったりする。
疲れを甘く見て放置していると、うつ病などの精神疾患になってしまう可能性も。そのような事態になる前に、自分の疲れを自覚してきちんと休息をとるようにしないといけませんね。
脳が疲労する原因
では、なぜそんなに脳が疲れるのでしょうか?
それは、高度に発達した情報社会の中で、インターネットやスマートフォンの普及により、情報が光の速さで飛び交い、現代人が1日に触れる情報量が増加しているから。
総務省が日本で流通している情報量を推定した結果、1日DVD約2.9億枚分にも達する。という調査結果も報告しています。
簡単にコミュニケーションが取れて、情報の溢れた便利な時代になったのは確か。しかし、一つ一つの問題に対する速い判断が求められたり、情報の処理が追いつかなかったりする。
大容量の情報処理を一気に行うことになると、脳が処理しきれない状態になってしまうわけですね。
今の時代は、脳も疲れるわけですよね。
脳が疲れる脳疲労とはどのような状態?
脳疲労は、脳が疲れて正常に機能しなくなっている状態ですね。
脳を使いすぎることで、脳に炎症(活性酸素)を蓄積させてしまう状態です。活性酸素が溜まり『酸化ストレス』の状態になると、有害な作用が引き起こされるのです。
脳を使いすぎるのも怖いですね。
そう、脳疲労は脳が操っている『自律神経』に有害な作用が加わり『自律神経』が正常な機能を果たせなくなってしまっている。ということなのです。
前にも説明したように、この自律神経には、『交感神経』と『副交感神経』の2つの反する神経で成り立っていて、呼吸器・循環器・消化器の臓器は、この自律神経のスイッチで、活動的に動かしたり、リラックスさせて休息をとったりと、バランスをとりながら身体の状態を保っています。
全ての体の機能を司る自律神経が『酸化ストレス』にさらされることで、身体の不調を起こす引き金となってしまいます。
脳を整え、脳疲労を回復させることによって、身体的な症状の改善が見られる可能性だってあるのです。
脳の疲労度をチェックするためのサイン
実は『飽きる』『眠くなる』は疲労のサインですの。これらのサインが出ているときは、とても疲れています。
長時間のデスクワーク、パソコン作業で、脳を使い続けると頭がぼんやりする、首や肩が凝るといった状態ですね。
つまり『飽きた』という感覚を感じたことはありませんか?
特にこの飽きたという感覚が、脳疲労のサインの1つになるそうです。
これ以上、この神経細胞を使わないで!
というアラームが、飽きるという感情になり現れると言われています。
もし、作業をしていて『飽きたな』と感じたら、まずは休息をとる、違う作業に切り替えるなど、脳の疲労を溜める前に、早め早めに対策するのです。
脳の疲労が蓄積されて、脳が身体の生体アラームとして効かなくなると、疲れが溜まっていることすら感じなくなってしまいます。
疲労感を感じなくなると人体としてもっとも危険な状態で、過重労働で重篤な病気、または過労死につながることだってあります。
日本の一般成人の約60%、人口の3分の1が慢性疲労を抱えていると言われています。早めに自分自身の身体のSOSサインに気付き、こまめに解消していくことが大切ですね。
脳の疲労を回復させる5つの方法
脳が疲労を感じることで『痛み』『疲れ』『気持ちの沈み』など、身体へ様々な影響を及ぼしています。
こうした症状を改善するためには『脳を整える』意識を持つほうがいいのです。
そして、脳を整えるにはどんな方法があるのか?
ここからは、日常生活に簡単に取り入れられる脳の疲労の解消法を5つ紹介します。
<睡眠の質をあげる>
睡眠は、昔から
●バランスの良い食事
●適度な運動
と並んで、健康的な生活を送る上での基本の一つです。
そして、脳を疲労回復する上でも、最も簡単にでき、重要な疲労解消法は『良質な睡眠』をとることにあります。
睡眠には、大きく分けて『レム睡眠』と『ノンレム睡眠』の2種類があり交互に現れます。
レム睡眠では、
脳が活発に動いて起きた状態で、身体は弛緩され、休んだ状態。
ノンレム睡眠では、
大脳も身体も寝ている状態で、頭の疲労を芯から回復している状態。
ノンレム睡眠では、体と大脳の疲労を回復しているだけでなく、入眠3時間後には成長ホルモンの分泌が活発になります。成長ホルモンは、年齢と共に分泌量は減ってしまいますが、お肌や筋肉の疲労回復など、細胞の修復に役立っています。
厚生労働省のガイドラインによると、適切な睡眠時間は、25歳~45歳までは約7時間、45~65歳までは6.5時間、65歳以上は6時間ぐらいと提唱されています。
しかし、脳疲労の回復には睡眠時間の長さだけではなく質の良い睡眠をとることがポイントで、質の良い睡眠をとるためには、仕事から帰宅した夜の時間の過ごし方が大切になります。
音楽やテレビをつけたまま寝ると脳が休まらないので、なるべく静かな環境が理想です。光を浴びると脳は活性化されてしまいます。
寝室は、遮光のカーテンを使用する、雨戸を閉めるなど、光を遮断して明るすぎない照明を使用するようにするといいですね。
入眠前にはブルーライトを発する、パソコン・テレビ・スマートフォンは、なるべく避け、目から刺激が入らないように意識しましょう!
体の深部体温が下がるタイミングで脳が眠気を強く感じるので、入眠する1~2時間前に入浴すると入眠しやすくなります。
熱めのお湯に肩まで浸かってしまうと交感神経が優位になり自律神経の疲れを誘発するのでNG。ぬるま湯のほうが副交感神経が優位になるので、リラックスして就寝に適した環境へ導いてくれます。
<食事でも脳疲労は回復する>
食べ物によって身体ができていると言っても過言ではないほど、健康的な身体を作るためには栄養素が必要になります。
タンパク質・脂質・炭水化物・ビタミン・ミネラルの五大栄養素の他にも、疲労回復につながる食材を上手に選んで、バランスよくプラスしてみましょう。
また、疲労を引き起こす原因となるのは、活性酸素による酸化ストレスと言われています。酸化ストレスには『イミダゾールペプチド』を意識したほうがいいですね。
このイミダペプチドは、人や動物の骨格筋や脳にある、2種のアミノ酸結合体の総称。
骨格筋や脳は、日頃の活動で、活性酸素が発生しやすく疲労も蓄積しやすい部位ですが、イミダペプチドは、その骨格筋や脳で再合成されて、抗酸化作用を発揮します。
イミダペプチドは、1日あたり200mg、最低2週間ほど摂取し続けることで抗疲労効果を発揮します。
200mgのイミダペプチドは、鶏の胸肉であれば100g食べることで摂取できます。鶏肉以外には、マグロやカツオなどの大型魚にもイミダペプチドは多く含まれています。
さらに『クエン酸』も抗疲労に作用する成分としてあげられます。
クエン酸は、レモンやグレーププルーツなどの柑橘系・梅干し・酢などの酸っぱさの酸味を持つ食品に豊富に含まれています。
クエン酸の抗疲労効果は、イミダペプチドとは違ったメカニズムで作用します。
通常、細胞が酸化ストレスによりエネルギー不足になると、疲労が蓄積していきます。この時にクエン酸を摂取すると、クエン酸がエネルギーを産出して疲労感を軽減してくれるのです。
でもクエン酸で疲労の軽減には繋がるけど、疲労の大元の活性酸素の発生は防げません。活性酸素を放置しておくと酸化ストレスにより疲労が蓄積してしまいます。
なので酸化ストレスに影響力のあるイミダペプチドと、疲労感を軽減するクエン酸と異なるタイプの栄養素を組み合わせて摂取することが最も重要ポイントになります。
疲労回復を軽減できる栄養素を理解して、食生活に上手に取り入れ、ストレスなく脳の疲労を解消していけたらいいですね。
<瞑想で脳の疲労を解消する>
瞑想と聞くと少し怪しげなイメージの方もいますよね。
でも、瞑想の歴史は古く、身体のリラックス感を増大させ、精神的なバランスの改善や病気の治療などにも利用されてきました。
瞑想を行うことで、脳の『前頭前皮質』という部分が活性化されます。前頭前皮質は、前頭前野とも呼ばれ、集中力・記憶力・意思決定といった認知能力に関係する領域になります。
認知能力は『脳の実行機能』とも呼ばれ、高いパフォーマンスを出すために最も大切な能力で、瞑想にはこの認知機能を向上させる働きもあります。
瞑想をする上で、大切なポイントは『①調身』『②調息』『③調心』の3つです。
まず、『①調身』=身体を調(ととの)えること。
背筋を伸ばしたら、肩の力を抜いてリラックスする。
一度肩をすくめるように力を入れてから、脱力してストンと肩を落とすと、適切な姿勢を作ることができます。
椅子に座って行う場合は、両足は床につけて、両手は太ももの上に置いて軽く握りましょう。
目は閉じてもいいですし、瞼を少し開く半眼にして、1mくらい先をぼんやりみても良いでしょう。
次に、『②調息』=呼吸を調えること。
5秒くらいかけて鼻から息を吸い、10秒から15秒かけてゆっくりと、鼻か口から、息を吐きましょう。
最後は、『③調心』=精神を調えること。
基本的な調心は、一つの対象に集中するもので『集中瞑想』と呼ばれています。
集中瞑想は、自分の呼吸や目の前にある対象物など、ひとつの対象に注意を集中させます。
瞑想をしたことがない方は、この『集中瞑想』から始めて、最初は呼吸に集中するのが、良いでしょう。
<小まめに小休憩をとる>
仕事の作業中でも、自動車の運転の最中でも『飽きた』と言うサインは脳疲労の最初のサインになります。
この最初の疲れの兆候が現れると、脳の情報処理能力が下がってきます。
疲れた脳が『これ以上使わないで』という信号を送っているので、一旦作業をやめてトイレに立つ、ちがう作業に取り替える、と気分転換をしてみるのがいいですね。
3時間ごとに15分の休憩を入れるよりも1時間ごとに5分ずつ、休息を入れる方が、脳の情報処理の低下も防ぐことができて、パフォーマンスの低下を未然に防ぐことが可能になるそうです。
<背筋を伸ばし呼吸をする習慣>
パソコンやスマートフォンを使うと、背中が曲がって猫背になりやすくなります。
背中が曲がっていると横隔膜を使うことができないので、自然と呼吸が浅くなり脳へ十分な酸素を送ることができなくなります。
また、息を吸うときには交感神経が、息を吐くときには副交感神経が優位になっているので、リラックスした状態を生みやすくなります。
ゆっくり息を吐くと、体内に二酸化炭素がたまります。血液中に、二酸化炭素が行きわたると、幸せな気分をもたらす神経物質であるセロトニンの分泌量が増加します。
セロトニンは、気分や感情の高ぶりを抑え、衝動的な行動を抑制する効果があるので、ストレスやイライラが取り除き、心をゆったりした状態に導いてくれます。
5秒くらいかけて鼻から吸い込み、吐く時は口・鼻のどちらからでもいいので10秒から15秒くらいかけてゆっくり吐き出します。
1日に緊張状態や興奮状態の時間が長いほど脳は疲れるので、小休憩を挟みながら姿勢と呼吸を整える時間を作ってみるといいですね。
と言うことで、5秒で鼻から吸って、10秒かけて吐く。
やってみましょう!!!